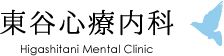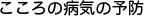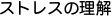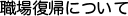喪の仕事 つづき
前回の続きです。喪の仕事を成し遂げていくということは、どういうことなのかと考えてきました。まずは私の住職としての経験を書きます。
私の寺で葬儀やご法事をした時に意外に思ったのは、私が思ったほどには亡くなられた方の話題が多くないことでした。ご法事をしているのだけれども世間話というか、亡くなられた方以外のお話を聞くことが結構多いのです。これはどういうことなのだろうかと考えました。日本ではあまり言語化してもの仕事を進めるという感じが弱い気がします。それよりも雰囲気やかたちが優先される様に思います。
よく外国人、特に西洋人では。パートナーがなくなった時に自分も死んでしまいたいとかもう生きていけないとか激しく感情を発露して、周囲の人が自殺でもするのではないかと心配して付き添っていた、という話を聞いたことがあります。でも実際はそういう人が、その半年後に再婚していたりするのです。喪の仕事が終わったのかなと思われます。区切りがついたのでしょう。
日本ではそれとは異なるように感じます。葬儀の後に以前には(今でも行っている方はたくさんおられます)1週間ごとに初七日、二七日、というように七日参りをおこない、納骨は四十九日忌、その後に百か日忌、一周忌、三回忌と続きます。心の動きと連動して考えてみると、大きな変化があった時には2ヶ月後が疲れが出ますので、四十九日忌付近はとても大変な状態であると言えます。その時にご法事をしてみんなで集まって当地では納骨をするのは、皆さんの力を借りて苦しい状況を乗り越えようという形に見えます。また百日後は約3ヶ月を過ぎところなので、少し落ち着いてきたという時期ですね。その後一周忌、三回忌とご法事があります。経験的に大きな区切りになるのは3回忌、つまり丸2年後ですね。上記に述べたように大きな区切りです。3回忌までは法要をしていてもみんさんが悲しみを引きずっている雰囲気があり、その後7回忌になると全く感じが変わっていることが多いのです。
私は長い期間にわたって法要を勤めてきた経験から、この法事という「かたち」、法事という「場」をみんなで共有することが、皆さんのこころのなかの「喪の仕事」そのものなのではないかと考えるようになりました。法要をすることでこころの整理をしている、という感じでしょうか。そういう仏事以外でも、相続の手続きをする、役所の事務手続き、遺品の整理をするとか、何かしら亡くなった方に関する行動をすることが喪の仕事につながるのです。喪の仕事はこころの中で行われるのでじっと瞑想していればよい、というものではないと感じます。
私はミステリードラマが好きでよく観るのですが、自分のお子さんがなくなったという設定で、部屋をこどもの生前のままにそのままにしておくというシーンがあります。あれは喪の仕事を止めているのだと理解しています。意識して整理しないようにしているように見えるのです。かなしみをそのままにして時間が過ぎるのを待っているように感じます。実際にはそうなるとなかなか前を向けないのです。
ですから目の前の出来事をに対してひとつひとつ行動をしてくことが気持ちの整理になるのです。けりをつけていくという感じでしょうか。私個人でいえば、一周忌に向けてお内仏(仏壇)を改修する作業をしています。また法事にどなたに来ていただくのか、どこで食事をするのかなどを検討しています。そんな行動が新しい生活、ステージに向けての準備なのだと理解をしているところです。もしかしたらこの文章を書くことがわたしの喪の仕事のひとつなのかもしれないなと今は感じています。