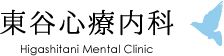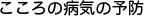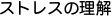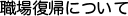雰囲気を感じること
年度が替わってから、適応障害の方がたくさん受診され、余裕がなくなっておりました。久しぶりのブログになります。
原因が明らかにあり、その後に体調の不調が出現して生活に支障が出てくる状態が適応障害になります。春は異動や昇進、転居、進学など生活の変化が非常に多い時期です。それに遅れること2-3か月の間に気持ちの落ち込みや不眠、倦怠感、動悸、息苦しさなどの症状が出現してきます。
実は外来で診察するときには、もちろん原因になった出来事や体調の不良について患者さんからお話を聞くのですが、実は言葉のほかに大事なのは雰囲気です。苦しそうな表情、せわしなく体がごいているようす、誰かに不満があるような感じなど。私の感覚では、断崖絶壁があってそこから転落すると死んでしまう、そのぎりぎりの崖から患者さんはどれくらい離れているのか、を感じるようにしています。この方はもう30センチくらいで落ちそうだ、この社員さんは2-3メートル離れているかな、この管理職の方はかなり離れているな、などです。
多くの方は休業に入って1週目ですでに、1‐2メートルほど崖から遠ざかっていくことが多いです。同時にお話をしている患者さんの背景に後光のような光というか、肩のあたりの明るさというか、それを感じて言葉にすると、患者さんの反応が良いのです。以前からその感覚は自分で持っており自分の判断に用いていましたが、最近はそれを積極的に言葉にしています。「肩のあたりの雰囲気が良くなったね」「何か今日は後光がさしているというか、元気になったように見えますよ」など。
日本人、特に男性は自分の内面を言葉にすることが苦手な人が多いように感じます。「出勤すると頭が痛くなる、会社の門をくぐると吐き気がする」と訴えるので、「では会社に何かストレスがありますね」と尋ねても「大丈夫です」とこたえるケースは少なくありません。そうなると言葉だけで進めていくことが難しくなります。そんなとき、まずはその人の雰囲気に合わせる、という方法から入ってどんな対応があるのかを探っていくことになります。
以前アメリカに留学していた方からお話を聞いたことがあります。少し風邪気味の時に「体調が悪いのではないか?」と尋ねられ、本人が「大丈夫だ」と返事をしたら、その後は全然声をかけてもらえなかった。また「来週にパーティーがあるけど来ないか」と誘われた時に「行かない」と一度返事をしたら2度と声をかけてもらえなかったとのこと。この辺りは「言葉がすべて」という文化を感じます。日本人だったら「大丈夫だと言っているけれどもやっぱい元気ないよ」とか「来られないって言ってたけれども、待っているから来てよ」などと、言葉だけでない部分でのコミュニケーションがあるように思います。この話は深いです。またの機会に触れることになりそうです。