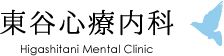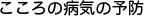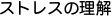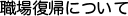喪の仕事
久しぶりのブログとなりました。私の個人的な話で恐縮ですが、母が昨年7月に亡くなり、しばらく相続やら何かとあわただしい日々を送っておりました。入所が長くなっていたので私たちの実際の生活はそんなに変化がないはずなのに、少しずつ何かが変化しています。それでもそろそろ1周忌が近づいてきて、何か区切りになりそうな気がしています。今回は親しい人が亡くなった時のことについて書いてみたいと思います。
急病や事故などで急に親しい人が亡くなった時が一番典型的なのでまずはそんな状況を想像してみてください。直後にはいわゆる信じられない時期があり、その後も不安定な精神状態が続き、なかなか気持ちが安定するまでには時間がかかります。こんな時に心の中で行われている作業、プロセスが「悲嘆の仕事」とか「喪の仕事」と呼ばれます。目の前で人がなくなったという現実があっても、心の中でその事実を納得して落ち着くまでには時間がかかるのです。
ご本人が大事にしている対象を失うことは対象喪失とよばれ、家族肉親だけでなく例えば大事にしていたペットが死んだ場合、あるいは病気や事故で体の機能が失われた場合などにも同様のことが起こると言われています。段階として諸説ありますが、おおよそこんな感じでしょうか。
対象を失った当初は失ったことを事実を事実として受け入れられない、信じられないという時期があります。次に感情の揺れが起こり、気持ちが不安定になります。混乱したり、失ったことに向き合って強い思慕の感情に駆られて悲嘆が始まります。喪失を受け止め始めたという時期です。どうして私たちをおいて・・・、亡くなった本人は幸せだったのだろうか、あの時にこうしていれば、なんとか戻ってきてほしい、もっとこんなことをしてあげたかった、などなど。特に自死の場合などはご自分を責めてしまったり、・・いろんな感情が渦巻きます。まだまだ失った対象と自分が一体化しているような状態と言えます。
その後次第に現実を受け入れられる様になってきて、対象喪失に向き合っていきます。そうなると気分が沈んだ抑うつ状態が見られます。これは個人差がありますが長期間続くことがあります。亡くなった人と自分が離れていくという感じでしょうか。その時期を経て、悲しんでばかりはいられない、自分のこれからを考えて行かなければという再建の時期に入ります。この喪の仕事に要する時間は人によってさまざまであると言われます。
物事は現実が変わってしまったからといってすぐに気持ちやからだがついていくわけではないということになります。よく頭ではわかっているのだけれども、腹落ちしない、どこかで納得できない、という感じがあります。頭とからだがしっかりと事実を受け入れて全体として前向きになれるにはそれなりの時間がかかるのです。中にはなかなか体調が上向かない、調子が悪い状態が続いている、何かしら動悸や頭痛などからだの症状が出る、など前向きになれないと訴える方がおられます。
外来での出来事を書いてみます。夫を事故あるいは急病で無くされた奥様が不眠を訴えて受診されることは珍しくありません。ある方は花瓶一つ移動するにも夫に相談してが決めていた、なんでも夫に頼っていたので一人になってどうしてら良いかわからない、とおっしゃっておられました。病気という感じはしないものの、とても苦しそうであり、軽い睡眠導入剤や時には抗うつ薬などを処方します。メンタルヘルスは3か月単位といつも申し上げている通り、3か月くらいの単位で変化があるものですが、結構時間がかかるものなのですが。このケースでは、「もう大丈夫みたいです。夫はいないのだから自分で決めるしかないったな」と明るく喋れるようになられたのは約2年後でした。それくらいもの仕事には時間がかかるということなのです。
ではどんなことをするとこの喪の仕事を上手に進められるのでしょうか。次に書いてみたいと思います。